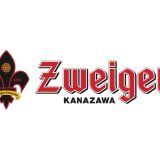先日、東京への出張ついでに、以前個人事務所を構えていた神保町にふらっと寄ってみたときの話。
2022年まで LIFT のオフィスがあった場所は現在中国語のランゲージスクールになっていて、窓から見るかぎり当時のレイアウトはそのままに、居抜きに近いかたちで使われているようだった。オーナーから「原状回復しないでOKです」と言われる程度にはキレイにリノベして退去したので、そのまま活用されている様子に妙な喜びを感じた。
折しもお昼どきに差し掛かっていたのでランチでも摂ろうと、ある店に寄ってみた。コロナ禍だった2020〜21年に、おそらく最も通い詰めたであろう神保町の裏通りにある居酒屋である。
なぜ通い詰めていたかというと、その店の鶏料理がどれもおいしかったというのもあるが、当時の緊急事態宣言やまん延防止等重点措置(まん防)の影響で周辺の店が軒並みシャッターを下ろしつづける中、一人気を吐いて昼夜営業されていた店だったからだ。にじみ出る飲食店としての矜持のようなものを、私は一方的に感じ取っていた。
当時は、政府からの営業中断要請に応じた店舗には協力金・支援金が支給されていた。お店を開けていても(そもそも街に人は歩いていないので)客は来ないわけだし、営業時間は常に短縮を余儀なくされている。各店は何としても固定費を下げて延命しないといけないので、行政からの要請に応じない理由はない。かくして、2020年の春から冬にかけては本当にどの店も開いておらず、普段は人で溢れている神保町もあの時期はさながらゴーストタウンのようだった。
そんな中で、その店はずっと営業していた。
店を開けているので支援金は満額出ないし、開けてもお客さんは少なく、運営は苦しかったはずである。
それでもなぜ営業を続けるのか。理由を聞こうと思ったこともあったが、「毎日店を開ける」というその姿勢から店主の気合はじゅうぶんに伝わっていたので、わざわざ聞くのも野暮だろうと、こちらもただひたすらに通い詰めることにした。振り返ると、昼と夜の両方その店で一人で食べた日も多い。
そんな客は珍しかったのかもしれない。徐々に入退店時に言葉を交わすようになり、金沢に移転する際には挨拶に伺うまでになった。
最後に伺ったのが3年半前なので営業しているか心配だったが、近づいてみると当時と変わらぬ門構えで「営業中」の張り紙が貼ってあってホッとした。中に入ると少し早い時間帯だったためか先客は私のほかに 1 名しかおらず、奥のカウンターに通された。
カウンターの前には厨房があって、当時とは少し風貌が変わった店長が、当時と同じように忙しなく動いている。
目が合えば声をかけようかなと思ったが、当時は足繁く通ったもののすでにあれから3年半が経っているし、私は当時より一層髪の毛が薄くなり、白いものも増えている。「誰?」となってしまう可能性も高い。仕込みの準備でずっと下を向かれているのを幸い?に、声はかけないことにした。
当時よく頼んでいた特製親子丼定食(ランチとしては少し値が張るが、ほんとうにおいしい)をオーダーすると、しばらくして配膳の方が「お待たせしましたー」とカウンターにお盆を載せる。いただきます。
当時と変わらぬ味に舌鼓を打っていると、カウンターから急に声がかかった。顔を上げると、店主がこちらを向いている。
「前から失礼します。これ、サービスです。」
両手には揚げ鶏の小皿があった。
「えっ?」
「あのー、金沢に行かれた方ですよね。お久しぶりです。」
「ああ、憶えててくださったんですか。ありがとうございます。ちょっと仕事で近くまで寄ったので、久しぶりに来てみました。どうされているかなと思って。」
「嬉しいです。何とかやってます。何だかお互い少し歳をとりましたね。ぜひ、ゆっくりしていってください。」
憶えていてくれたのか。
不思議な気分のまま残りを平らげ、会計時に少しだけ挨拶し、店をあとにする。
コロナ禍のあの頃は、先行きの不透明さに多くの人が閉塞感を感じていた。もちろんあの環境下だからこそ萌芽したビジネスや習慣もあるわけだが、当時の飲食店が受けたダメージは計り知れない。
だからこそ、あの静まり返っていた裏通りにポツリと灯っていた店の明かりは、単に「店が開いている」以上の意味があった。そう思ったからこそ私はあの店に通ったのだし、店主もきっと逆の立場で、何かを感じてくれていたのかもしれない。
また機会を見つけて伺おうと思います。