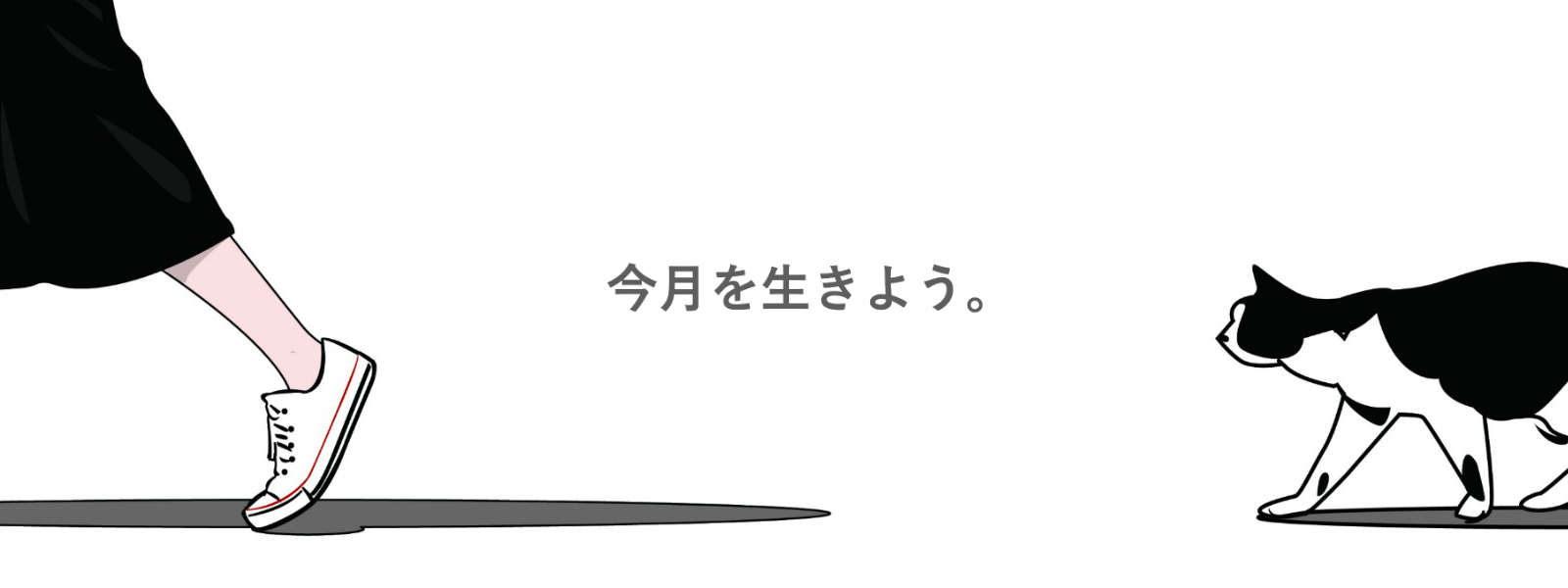東畑開人さんの『心はどこへ消えた?』の中に、こんな一節がある。
身の回りで仮病を使っている人を見かけたら、その演技に乗ってあげるべきだ。例えば、子供が仮病を訴えているなら、エビデンスの提出を求めるのではなく、脚本に沿ってケア役を演じてあげる。心配してあげ、休養を取らせてあげる。こういうことだ。目には目を、演技には演技を。仮病を癒すのは、仮治療なのである。そうじゃないと、「心の風邪」は「心の肺炎」にまでこじれてしまって、長期療養を余儀なくされてしまう。後遺症が残ることだってある。
『心はどこへ消えた?』 P162
私は小学校のころ、時折仮病を使って学校をズル休みしていた。東畑さんもそうだったらしく、本書には「体温計を繊細に擦りながら仮病に最適な 37.4℃ を目指す」というエピソードが出てくる。私も近似値の 37.3 ℃ を目指してがんばっていた小学生だったので、思考回路としてはほとんど同じだったと思う。(0.1℃ だけ私のほうがコンサバだが、これは各家庭の親の判断の閾値の差だと感じている)
学校に行きたくない時期は小学校の3〜4年生ぐらいがピークだったが、特に誰かにいじめられていたというわけでもなく、先生が苦手ということでもなく、ただ何となく「疑わしい」と感じていたからではないだろうか? と振り返って思う。
クラス替えで教室が別々になったり、習いごとやちょっとした放課後の予定が合わなくなったり、そういったほんの些細なイベントによって小学校の友人関係はかんたんに変わってしまうものだ。実際、無視されることはないまでも、友人だった頃の記憶が喪失しているのか?と訝しんでしまうそっけない態度をとる子は珍しくなかった。
私はそういった場によって人間関係が突然に変わる(関係が場の奴隷になる)脆いつながりを小さいながらもどうやら感覚的に疑っていたようで、その疑わしい関係性の中で何とか成立している日々が不安だったのかもしれない。とにかく何となく学校には行きたくなかったし、行きたくないポイントが飽和すると、仮病を使って休んだ。
母は私の仮病におそらく気づいていたはずだが(なにせ私は大根役者だった)、仮病を咎められて強制的に学校に行かされることはなかった。そんな余裕はなかったのだと思うし、母によるケアの演技だったのだとも思う。
共働きだったので仮病の日は家に一人ぼっちになることができた。ゲームをやっていた形跡が残らないようにファミコンに勤しみ(帰宅時間の1時間前には終わらせ、カセットは慎重に元に戻した)、ノートに迷路を書いたり、図鑑を読んだりしていた。仮病の日は楽しかった。
そんなことをしているうちに学校に行きたくない時期はなんとなく過ぎ去り、6年生ごろになると仮病は使わなくなった。
社会に出てからも、小学生のころに違和感を感じたあの脆く疑わしい関係性は引き続き存在していて(何なら脆さは強化?されていて)、生きているあいだはずっと付き合わなければいけないものだと知った。
同時に、脆さは曖昧さでもあるので、年をとるにつれて曖昧さへの耐性がついてきたことで違和感を感じにくくなってきたという実感もある。
脆いものを壊れないように丁寧に続けていくのは楽しいし、脆いからこそどうしようもなくなったらリセットすることもできる。世の中はとかくいろいろあるけれど、「あなたは元気に学校に行ってもいいし、体温計を擦ってもいいのだ」という前提を自覚することによって得られる判断というものがあるのではないだろうか。
と、水泳教室に行きたくないとぐずる息子と、テレビから流れてきたある悲しいニュースを見て思いました。