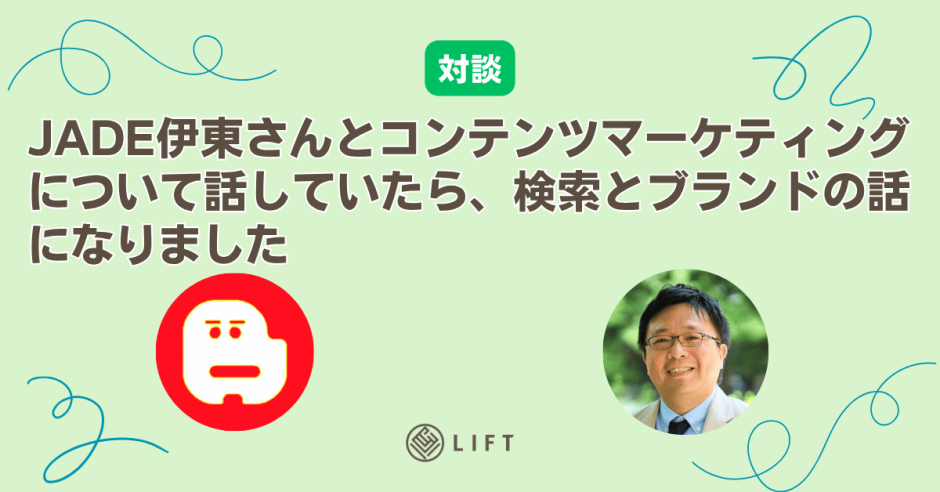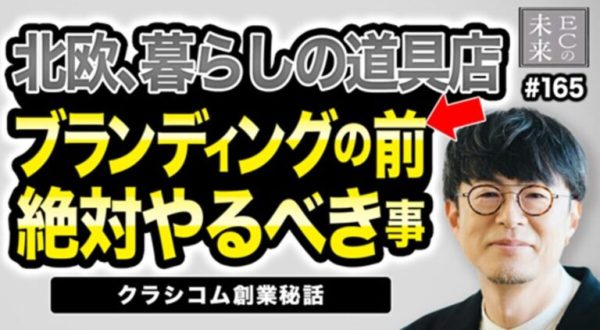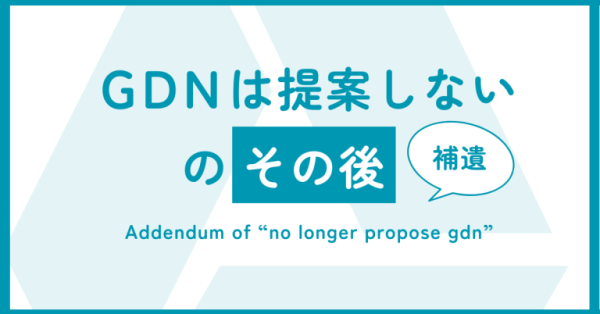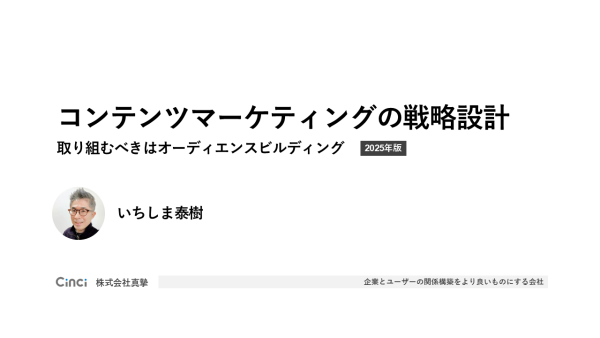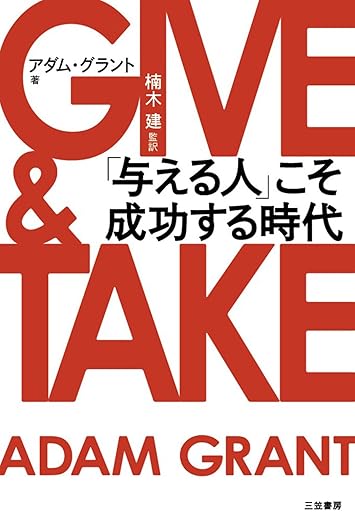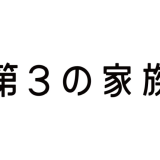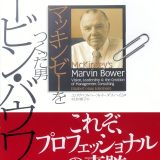JADE のことを「泣く子も黙る梁山泊集団、近づいたら火傷しそうだぜ…」と、そんな風に思っていた時期が私にもありました。
「インターネットを良くする会社」って、思ってもなかなか言えない。スゴイ
ふとしたきっかけで代表の伊東さんが執筆していらっしゃる JADE のニュースレターを購読しはじめたところ、その圧倒的な筆致と面白さに度肝を抜かれました。「デジタルなのに筆圧がある… 毎週のようにこの熱量で書いてるのはすごすぎる!」と、一読してリスペクト。
伊東さんが折に触れて言及されていらっしゃる「コンテンツマーケティング」について、改めてご本人にお聞きして、できればどこにも着地しない話をゆっくりしてみたいな〜と、そんなゆるい目的(すみません!)でお伺いしました。
JADE という、デジタルマーケティングを非常に高いレベルで提供されている企業の代表でもあり、同時に優れたコンテンツマーケターでもある伊東さん。せっかくお話する機会があるのであればその内容をテキストに起こしてみたい、と、ご了承を得て対談記事として公開します。
…などと冒頭から妙に力が入ってしまいましたが、中身はゆるい雑談形式ですので、「お、雑談だな〜」と思いながら読んでいただければ幸いです。

株式会社JADE 代表取締役社長 兼 最高執行責任者
伊東 周晃
いとう のりあき
1975年奈良県生まれ。2000年に株式会社NKB入社。2004年より東京メトロと共同運営する地域情報サイトの立ち上げ、運営に参加。 2007年10月株式会社ぐるなび入社。「ぐるなび」を中心にSEO及びソーシャルメディア施策、ウェブ解析、コンテンツマーケティング、広告、広報領域の執行役員をつとめた。
※この対談は 2025 年 8 月に行われました
コンテンツマーケティングはどういう時間軸なのか?

今日はよろしくお願いします!
伊東さんが書いていらっしゃる JADE のメルマガを毎回楽しみにしてまして、せっかくお話しするのであればテーマはやはり「コンテンツマーケティング」だろうと。今日はそのネタ一本で参りました!
ほぼ丸腰ですね!メルマガもお読みいただき嬉しいです。まだの方はこちらからぜひお願いします m(_ _)m

2025 年 8 月 19 日配信のニュースレターのタイトルが、『「生き残る」ことを考えたら、無意識にコンテンツマーケティングにたどり着くのかもしれない』でした。その中で、北欧暮らしの道具店のクラシコムさんについて書かれた、コマースピックさんの記事(動画)に触れていらっしゃいます。
お読みいただきありがとうございます。はい、実は動画の中では一度も「コンテンツマーケティング」という言葉は使われていないんですが、やってることはまさにコンテンツマーケティングそのもので。なんというか、見事だなと。それで言及しました。
記事は動画と合わせて3部作ですので興味ある方はぜひ通してご覧ください

伊東さんが「観るべし!」と強く推されていたので、私も拝聴しました。まず響いたのが、「急がなくていい」「時間的に余裕があることが強い」というクラシコム青木さんのお話です。紹介されている動画は三部作になっていて、確か二つ目の動画で言及されています。
これは私も本当に心から賛成で、むしろほとんどのトラブルは「急いでいること」「期日が判断の妥当性よりも優先してしまうこと」に起因するんじゃないかと思っているくらいです。
いやー、わかります。大抵のビジネスは比較的短いスパンで評価したり意思決定しないといけないですよね。トラブルや不具合、うまくいかなさと、求められる速度との関係性は感じます。

私は何事も「どの尺を優先するかで物事の判断は大きく変わる」と捉えているんですけど、たとえば上場企業であれば四半期単位で報告の義務があり、マーケットはそれで判断しますし、現場レベルであれば評価がそれより短い月や週の単位だから、「月末までに数字をねじ込むぞ〜!」とかになる。
一方で、仮にそれが都市計画や教育制度であれば、何十年先を見据えて決めるほうが合理的です。求める時間軸によって判断・行動がおのずと規定されていく。
私が以前勤めていた会社では、とにかく「拙速でやれ」と言っていました。だいたい拙速でやるとトラブルが頻発して手間が 3 倍かかったりするんですけど(笑)、でも早くやること、速く動くことで場が盛り上がるという効用もあります。

確かにそれもありますよね。急がないといけないときは強引にテンションが上がるので、そこにモメンタムが生まれやすい。ビジネスである以上、スパンが短いのはある程度受け入れていかないといけない。
そう。だからどちらがいいとか、絶対的なことは言えないんです。
…言えないんですけど、でもやっぱり速さが当たり前になることで短期目線が常態化していきやすいですよね。

短期と長期を行ったり来たりできるといいんですかね?
先ほどのクラシコム青木さんの動画で面白いのが、輸入ビジネスの仕入れを確保するために、バイヤーの確保やネットワークを非常に短い期間で構築したというエピソードです。「急がなくていい」と言いながら、動くときはめちゃくちゃ速い(笑)。
決めるまでは時間をかけるけど、腹落ちして決めたらそこからは一秒でも早く動く。つまり「使い分け」ということなのかなと思います。

なるほどなあ。短長の二項対立はあまり意味がなくて、「この場合の適切な指標はどっち寄りだ?」という判断の精度がポイントなのかもしれないですね。
仮に短長どちらに理があるのかなと考えると、これは経営者や意思決定者の好みになっちゃうのかもしれないですけど、私は納得して動けるのは青木さんのようなやり方ですね。じっくりと、はやく。

決める人がどのタイプなのか、というのは大きな影響がありそうです。
乱暴にいえば「結果はあくまで副産物」みたいな言い方もできるんですよね。特にコンテンツマーケティングにおいては。

アウトプットはコントロールできるけど、アウトカムの量やタイミングはコントロールできない、コンテンツマーケティングというのはそういう類のものですよね。だから尺は長く取らないといけなくて、短くするとシンプルに成功確率が落ちてしまう。
うまくいってない組織を見るとだいたいみんな焦ってますね。結果を求めてせかせかしちゃっている。
尺が長くてアウトカムがわからない、なんて覚悟がいる取り組みなんでしょう… コンテンツマーケティング!
需要と供給のギャップ、あるいは広告について
もう一つ。先ほどの動画では、需要と供給のバランスについても言及がありました。たとえば北欧暮らしの道具店さんであれば、需要はあるけど供給が少ない分野が見つかったから、供給側のボトルネックを整備することで伸びたという。

あれもマジで真理ですよね。需要は喚起できたとしても短期的で、かつ中長期のコントロールはできないので、あらゆる課題は常に供給側にあるということだと思います。
製造業なんかを見ていれば、供給力の重要性がわかりますよね。

サプライを安定させて、瑕疵を可能なかぎり少なくすれば、スケールメリットによって原価が下がり、より拡大しやすくなる。
少し話題が飛んじゃいますが、個人的には、この話は広告やコンテンツにも応用できると思ってまして。
ほうほう。

昔はメディアが今より希少というか、テレビであれば局や番組の数で、新聞は頁数で、枠の限界は比較的想像の範囲内というか、まだ数えられるレベルで収まってました。
だから限られた枠の中でリーチが最大化できれば、枠は相対的に希少性が上がるので価値が保たれるわけですが、後から登場したインターネットはもはや宇宙みたいなもので、供給側が爆発的に増えるので…
サプライが一気に供給過多になる。

そう、コンテンツが無限に増えるので、ビューあたりの単価は割り算すると下がる一方で、上がりようがない。だから希少性を高めて単価を維持するか、単価が安くても量を確保するかの二択しかないんですけど、プレミアム枠を作れるメディアはどうしても限られてしまう。
そして徐々に単価は下がらざるをえない。なるほど。

一方で、いわゆるメガプラットフォームは量を確保できるから、質はあとから調整できるんですよね。角度や用途、利便性や希少性などを変えることで、プレミアム枠もつくることができる。
オープンウェブ側は量で劣るし、プレミアム枠が作れるのは一部のプレイヤーだけになるので、人が集まらない以上単価は下がり続けてしまいます。そうすると収益を確保するためにパブリッシャーは広告枠を増やし続けるしかないという地獄の入口が待っている。この悪いスパイラルの中で拡大したのが、今の広告だらけの記事と閲覧の邪魔をするディスプレイ広告なんだと思うんですよね。
受給バランスの話は広告にも置き換わるんですね。面白いなあ。

今は生成 AI による無限のコンテンツ供給が SEO 側で問題視されたりしますが、AI 以前もクラウドソーシングを使って大量に SEO で需要がありそうな記事を量産していくということがあったじゃないですか。
検索順位を上げて、そこからのトラフィックを広告で収益化していくと。製造原価が 1 ページあたりの広告収益を上回ればどんどん儲かっていくと、そういうモデルでしたね。

古い意味での “コンテンツマーケティング” って、そういうディスプレイ広告のレベニューシェアと密接な関係にあったと思うんです。でも、その方法は CPM に下方圧力をかけるので、やればやるほどデフレが止まらなくなる。そうなると広告は量を増やすしか売上を確保できなくなるので、どんどん過激化していくという。
このあたりにも似たようなことを書いてます
アルゴリズムとのいたちごっこの末、現在は AIO(AIオーバービュー)の登場によってそういうコンテンツは目立ちにくくなりました。

品質の高いコンテンツを提供していれば AIO の影響はあまりないのだと思いますが、いわゆるインフォマーシャルクエリやナビゲーショナルクエリと呼ばれる検索はゼロクリックで済んでしまうケースが増えてきました。メディアは検索結果からのトラフィックによって広告収入を得ていたので、CPM のデフレを増長させていたコンテンツメディアほど厳しくなっています。
なので、少し抽象的に言うと「AIO は、爆発したサプライと、限りあるデマンドとのバランスを調整するための動線整理である」という見方もできるなあと思ってます。
なるほど。インターネットは供給がコントロールできない、だから供給を制すものが市場を制すと。ここでもさっきの話につながりますね。

そういう環境下でどうすればいいのか?が、現代のコンテンツマーケティングの出発点というか前提になっているのでは?考えていまして。
きっとそれは伊東さんや真摯のいちしまさんたちがおっしゃっていること根っこが同じで、「オーガニックか? ペイドか?」みたいなレベルの区分けではなくて、もっと総合的に、包括的に考えろということだと思うんですよね。
いつも勉強させていただいております!
需要が増える方向にある?
ありがとうございます。少し話が各論に寄っちゃうかもしれませんが、Moz(当時)の Rand Fishkin 氏は「Google はオレたちのようなコンテンツを出す側が作ったんだ。そのオーナーシップを壊して、オレたちが得るはずだったクリックを一方的に奪っている」と。2015 年あたりからずっと言っていて。

はい。
その当時の文脈は、オーガニックのクリックを減らして広告の方に寄せている。つまりラベルを変えたりしてオーガニックと見分けがつかないようにしているとか、そういう話だったんですけど。今はそこから段階が進んで、 AIO でクリックそのものがなくなるかもしれないという騒ぎになっている。

クリックをオーガニックと広告のどちらに流すかという話ではなくて、ゼロクリックで目的が達成できてしまう世界ですよね。
そこで疑問なのが、仮にゼロクリックでユーザーは済むとして、Google にとってはクリックが売上の源泉として最重要の要素のはずじゃないですか。それがなくなっていくとどうなるのかなと。

そうですねー。まず事実だけでいうと、Google の、検索経由の売上はずっと伸びています。
そう、それはそうですよね。

じゃあなんで伸びているのかというと、さすがにこの規模なので、検索数の伸びは鈍化しつつある。だから検索数の増加率よりも広告のクリック率やクリック単価の上昇率の方が上回ることで高い成長率を維持しているという感じに見えます。
単価は自動入札でぐんぐん引き上がるけど、経済合理性を考えるとインフレ率を極端に上回ることは考えにくいから、長きに渡って無理なく売上を増やしていくためには、やはり検索数(サプライ)を増やす必要がある。
成長性は AI によって保たれるけど、成長の源泉を辿っていくとそれは人間の行動になると。

そうです。広告を出せるインプレッション、つまり検索結果はがんばって増やさないといけない。でも、先ほど挙がったように、ディスプレイ広告によって築かれたコンテンツのエコシステムはすでに壊れかけているし、オープンウェブのコンテンツの質が下がることによって可処分時間が SNS により流れやすくなる。この流れに Google はずっと前から危機感を抱いていたはずです。
ユーザーがどんどんそっちに流れていってしまうと、成長の源泉が枯渇してしまうかもしれない。

検索結果をクリックして飛んだ先のページの品質が低いのは、ユーザーからしたら検索結果の質が低いのと同義です。だから検索はコンテンツの汎濫によっていつのまにか不便なものになってしまっていた。再度「便利なもの」になる必要がありました。
20年前なら「回答を示す 10 のウェブサイトリンクを一瞬で提示すること」が便利だったわけですけど、今はリンク先に飛ぶとむしろ不便だから、飛ばなくても目の前に回答が示せればいいじゃないか、となりました。
Google という環境の中で答えが提示できれば、オープンウェブに飛ばなくてもいいと。

ですです。以前はオープンの権化みたいだった Google は、今は徐々にクローズドな空間を提供する存在になっていきまして、広義の SNS みたいになりつつあります。滞留して、何度も検索したり動画を見てくれればいいと割り切るようになった。
実際にクエリは増えていると言ってますしね。

Elizabeth Reid 氏が Google 検索の責任者になってからは、従来の「サイト送客」の役割からは転換しつつあることを明言していますしね。彼女は「Google が常時ユーザーをサポートする未来像を描いている」「検索は全面的な刷新でなく常に進化している」みたいな感じで話すことが多いですが、パブリッシャーに気遣いを示しつつも、「AIモード」なんかが象徴的なように、アウトプットに外部送客の文脈はありません。利用者を Google プロパティ内に留める方針は明確なんだなーと思って見ています。
結局ほとんどのユーザーは、答えが一瞬で分かればそれに越したことがないので、いわゆるインフォマーシャルクエリとかナビゲーションなクエリと呼ばれるものは、もう送客云々じゃなくてその瞬間に答えを出せばいいと。そういうことですよね。

はい。そういうクエリであればあるほどものすごい量になるのですが、もともと広告売上にはそこまで影響していなかった。ユーザーは答えがほしくて、企業はクリックや売上がほしい。そういう時に無理やり広告を出してもマッチングが悪いし、そもそも不便です。企業にとっても収益性が低いので入札は少なく、品質が低いから広告ランクを満たしにくいので結局出ない。出ないので売上貢献度も低い。
なるほど。そうするとやはり便利になってユーザーとクエリが増えた方が結局はいいんですね。

そう思います。便利になって利用頻度が増えたほうが、売上につながりやすいコマーシャルクエリの絶対値も増えていくはず。だから検索の数を増やすためには大前提として便利でありつづける必要があるということなんだと思います。
身も蓋もないかもしれませんが、ユーザーを囲って常に Google を使い続けてもらうほうが、質の低いパブリッシャーに気を遣ってユーザーに離反されるよりいいよね〜ということではないかと。
クリック率と指名キーワードについて
岡田さんの話をまとめると、仮にインフォメーショナルなコンテンツなどを獲得しているクエリが AIO に集約されてしまったとしても、Google の広告売上的には影響がなくて、むしろ今の課題は検索の成長性だから、Google というプロダクト自体をよりよい体験に変えていく必要があったので AI を組み込んで利便性を上げている。
だから取り組みとしては正しい方向であって、それは最終的にユーザーのクエリ増加となって売上に跳ね返ってくるだろう。そういうことですよね?

はい。おそらく 今後の Google の方向性によってパブリッシャーや企業のビジネスモデルは大きな改革のタイミングに入るはずなので、個人的にはインターネット上のコンテンツの質的側面だけ見れば、逆によくなることだってあるんじゃないかと、そんな期待すら持っています。
なるほどなー。私は SEO 側の意見を聞くことが多いんですが、やっぱりオーガニック側は「トラフィックが減る」「クリック率が減る」ということにすごく敏感なんです。でも、ユーザーが増えて検索の絶対数とクエリのバリエーションが増えないと自分たちも恩恵を受けられないわけで、個人的にはオーガニック・広告ともに増えていくんじゃないかなと思っています。

実はいろんな方法論や方向性がたくさんあるかもしれないのに、人はどうしても「減る」ことに目がいきがちですよね。得よりも損を多く見積もるように進化してきた生き物なので。
見ている数字の違いもあるかもしれません。サーチコンソールと広告の管理画面とでは、感じるものが違うだろうし。順位が上がっても、クリック率とかやっぱり以前とは違いますしね。

なるほど〜。確かに、そう言われたら広告側はクリック率をそれほど気にしていないかもしれません。例えば Google 広告のクリック率って、特に指名キーワードにおいてはここ数ヶ月でものすごく下がっているんですけど、これは AIO の影響というより、オークションのスロットを二つに分けた影響のほうが大きいんです。
指名ワードは広告ランクが高いので、上部スロットに出ない一般ワードでも、下部のスロットで並行してサーブされる。でも下部だからクリック率としては低いので、管理画面でみるとキーワード単位のインプレッションが増えて CTR は下がっているように見える。こんなことがよくあります。
※これだけ読んでも分かりにくいのでXで解説もしています
へえー。

でもキャンペーン全体の合計クリック数で見ると、シングルスロットの頃よりマルチスロット以降のほうが増えている。キーワード単位ではクリック率が減っているので焦っちゃうけど、インプレッションの機会が増えたぶん、合計のクリック数はむしろ増えているんですよね。
ラベルの色がちょっと変わるとか、ロゴのあるなしでクリック率が上下するといった変化に広告側は以前からけっこう慣れていたりもしますし、同じ率ならコンバージョン率のほうが大事。だからあまり気にしないという側面はあるかもしれません。
なるほど、SEO は順位やクリック率といったサイトへの入口のほうを見ていることが多いけど、広告はコンバージョンから逆算して見ていると。
そのお話に加えて、冒頭で言っていた時間軸も関わってくるかもしれないですね。SEO は広告よりも時間がかかる施策ですし、コンテンツマーケティングはさらにそれより一周するまで時間がかかります。

有料無料にかかわらずですが、想起がないところでがんばるより、最初から指名されたり選択肢に入ってたほうが費用対効果がいいに決まっているから、その意味でもコンテンツマーケティングは息が長くなるはずですよね。
指名されるためにやる。だからそのための活動は単独で ROI を見るんじゃなくて総合的に見ていったほうが合理的ですよね。短期的ではなく中長期的に指名キーワードを増やすためにも、他の活動で自社を知ってもらう機会を増やしていくことが必要ですので。
ブランドは受動態
指名キーワードの話が出たのでもう少し話すと、指名キーワードは英語だと Branded Term とか Branded Keyword というじゃないですか。これはよく考えると面白いですよね。

Branding Term とは言わないですもんね。
そうなんですよ。「Brand」は動詞だと他動詞ですから、この -ed はいわゆる受動態で、Branded Keyword とは「ブランドされたキーワード」ということになります。ブランディングではない。

知られる→探される の順番ですもんね。だから過去のある時点で「ブランドされた」状態になっている。受け身であり、過去分詞の形容詞的用法でもありますね。
まさに、自分から知ってほしいと言っている -ing の状態ではないですよね。知られた結果として検索される。受動態なのが指名キーワードです。

そういう意味では、広告でも配信対象を決める作業を「ターゲティング(Targeting)」といいますが、最終的に顧客から「選んでもらう」ことを優先するのであれば、同様に「ターゲテッド(Targeted)」になりますね。
Targeting は企業側からの視点であって、特にコンテンツマーケティングであれば「何かあった時に想起される」あるいは「選択肢に入る」ためにやるわけだから、コンテンツを見たり聞いたりしてもらう対象を決める作業は確かに Targeting かもしれないけど、営み全体としては Targeted ですよね。ユーザーから選ばれるためにやっているから。

Google はよく「Branded Keyword のほうが成長率は高いですよ」と言うんですが、広告視点ではインフォーメーショナルクエリ は AIO で即時回答するからレベニューには結びつきにくいし、先ほど話した 2 スロットのオークションで Branded Keyword のキャンペーンの表示機会は増えているし、SNS などでレコメンドされるものの大抵は固有名詞。そりゃ Branded が強いのは当たり前だよなあと思います。
そうですね。だから結局は「ブランドづくり」に話が戻っていく。

そしてその方法論が、ある意味でもっとも確立されていない。
だからこそ、「どういう存在として知られたいのか」が大事な気がします。社会に対して、自分たちの行動一つひとつの積み重ねによって知られることが、そのままブランドを作る行為につながると思うので。
もちろん、キャンペーンをドーンと打ってたくさんの人に知ってもらうという0→1の施策も、とても大事なブランド活動だと思うんですよ。知名度がゼロの「誰にも知られてない状態」「多くの人に知られている状態」とでは、何をやるにもすべてが違ってくるので。

「どういうものだと思われているか」が合っている前提で、接触量も大事ですよね。ブログもそうだし、動画、メールや LINE もそう。そういう一見地味そうだけれども、広範囲で接触機会を増やしながら、コツコツやっていく。まさに JADE さんがやられていることですね。
ありがとうございます。SEO を長くやっている身として、結局はトラフィックばかり気にしちゃいがちなのですが、仮にトラフィックを生んでいて記事として成立していたとしても、それで企業の存在を認知してくれているかどうかというと微妙なことも多くて。
やっぱり認知されて、その企業やサービスが「気になる存在」になってもらわないと Branded とはいえない。最近はようやく「JADE の記事読んでます」と言われることも増えてきて、うれしく思っています。

私もニュースレターを拝読するようになって「えっ、伊東さん毎回この熱量で書いてるの? マジで?」とびっくりして(笑)。これはリスペクトしないと…!みたいな気持ちに自然となりまして。それがなんやかんやで今日の対談に至っています。伊東さんのニュースレターがなかったらこうやってお話しすることもなかったかもしれないし、そういう意味で、ここまで含めてのコンテンツマーケティングだと思うんですよね。
うれしいなあ。たしかに岡田さんは JADE のメンバーの中でも知り合いが多いですけど、こういう機会はなかったですもんね。

はい、小西さんや村山さんなど、知っている人はいるけど、特に会社として絡む理由もなかったから特にこれといった機会もなく。。。でも、伊東さんの、JADE さんのコンテンツを読んで Branded されました(笑)。
これぞコンテンツマーケティング!(笑)
コンテンツマーケティングの持続可能性

話が尽きないのですが、最後に、私のもう一つの問題意識として「コンテンツマーケティングを続けることの難しさ」があります。どうしても成果が可視化しやすい短期的な施策と比べると不利で、ちょっとしたことで途切れてしまうことも多い。これにはどう思われますか?
たとえば本日の対談を一つの成果だとすると、記事やメルマガの各号にどう貢献度をアトリビューションとして割り振るのかって言ったら、もう無理じゃないですか。実際のところ。

無理です。ある号がきっかけで連絡したとしても、それは本当に「たまたま」でしかなくて、それ以前の背景や営みがあって初めて現れる「たまたま」ですもんね。
ですよね。だからこれがコンテンツマーケティングの難しさなんでしょうね。
たとえば上層部から「コンテンツマーケティングをやれ」と言われてやっている場合、その人は意思決定に関わっていないし、大きな権限もないことが多いから、どうしても今あるビジネスモデルを前提にして、それにフィットするようにコンテンツマーケティングを適用することになると思います。

そうなりますよね。
そこで次に起こることは、新たに加えられたコンテンツマーケティングと、すでに行われている施策とを並べられて「フラットに」評価することです。こうなると、だいたいパフォーマンスで負けます(笑)。

(笑)。
でも、ここまで話してきたとおり、コンテンツマーケティングは偶発的に起こりうる将来的なインパクトに対して投資するみたいな側面もあるじゃないですか。キャリア論でいうプランド・ハップンスタンス(計画的偶発性)理論みたいな。
だから、短いピリオドで説明しようとするとその重要な前提が失われてしまいますよね。
そうなんです。一つの企業の中の話だけでいえば、担当者レベルだと評価期間が短すぎてやり切れないことが多い。だからその人、担当者が偉くなるしかないんですよ。

コンテンツマーケターよ、偉くなれ(笑)!
先ほどの時間軸の話にもつながると思うんですけど、並列で評価するということは度量衡を合わせないといけない、同じ土俵で比べないといけなくて、そうすると月次とか四半期みたいなスパンで見ることになる。そんなの勝ちようがないというか、もうそんなことしても仕方がない。

だから結局は覚悟とか意思、あるいは責任みたいな話になってきますよね。
結局は順番が逆で、コンテンツマーケティングの担当者が偉くなるんじゃなくて、偉い人が覚悟をもってコンテンツマーケティングをやる、ということでしょうね。

まさに伊東さんだ!
いやいや、そんなことないです。
ちなみに私はニュースレターという方法に価値を見出しているのですが、そのきっかけが、以前 Content Marketing World などの海外カンファレンスによく行っていた 2010 年代後半あたりに聞いた、Ann Handly という方のスピーチです。
『多くの人はニュースレターを書く時に、「ニュース」と「レター」のどちらだと思っているか。多くの人は「ニュース」だと思っている』と。

ああ。
『だけどニュースレターは違うんだよ、「レター」なんだよ。』と、そういう話があったんです。
当時の日本だとコンテンツマーケティングは記事コンテンツの話が主流だったので、ニュースレターの話は新鮮でした。もちろんこの言い回しはちょっとしたレトリックではあるんですけど、個人的にはすごくインスパイアされまして。

面白いです。ギクッと気付かされますね。
当時からすでにコンテンツを作ったら伸びるという状況でもなくなってきていましたし、その後どうしようかなと私も悩んでる時期ではあったんですよ。
ソーシャルメディアにバズって一夜にして有名になるとか、そういう中毒性がある世界とは違って、ニュースレターというのはずいぶん地味な方法かもしれないんだけども、特定のオーディエンスとの関係を作っていくことのバリューみたいなところは、もしかしたら次の可能性としてあるのかも?と思い始めたのがその頃でした。

なるほど〜。
レターは贈る(送る)ものだから、Give(贈与)が先ですよね。そこで思い出したのが、Adam Grant の『GIVE & TAKE』という本です。伊東さんのおっしゃっていることは、ここでいうギバー(Giver)だなと。
どういうことですか?

ギブ・アンド・テイク(Give & Take)は、「Take がある程度見込める状態、それを前提として先に Give する」という順番のことだと思っている人が多い。順番は Give が先だけど最終的に Take でバランスされるはずだと、そんな感じの意味でみんなはこの言葉を使っているんじゃないかと。
でも、Take を前提にした Give は、必ずしも Give じゃないというか。たとえば Take ばっかりを求める人をテイカー(Taker)と呼ぶとしますと、常に奪おうとするテイカーとしてだけの人は、表社会だとうまく生きていけないじゃないですか。でも奪わないまでもより多くを受け取りたい、「与える < 与えられる」がおトクで望ましいと考える人は多いですよね。そういうテイカー寄りの人はどういう論理構造になっているかというと、Give & Take じゃなくて、Take & Taken なんだそうです。要するに「テイクしたいからテイクさせてやる」という考え方であると。
それは外から見たら実は「Give & Take」とあまり見分けがつかない。行動を描写したら Give に見えるんだけど、それは Take を前提とした Give だから、それは本人にとっては Taken(奪われる)ものになるので、Give ではないと。
行動が似たように見えても意図が真逆だということですね。

ギバー(Giver)でも似たような構造はあって、その場合は Give & Given になるらしいんですよね。Give が前提にあって、その結果として「たまたま相手から Give される」ことがある。だから Give & Given 。これも受け身なので、Branded と構造的にも同じですね。
ニュースレターは、まさに先ほどの「レター(手紙)」のレトリックでいうと、Give & Given の精神に近いですね。返ってこなくても構わないけど、贈りたいから送りつづける手紙のようなものです。

もしその手紙に見返りを求めるような外連味が見え隠れすると、 Take & Taken になってしまいますよね。人は誰しも Give & Take のバランスのどこかにいるはずなんですが、多くの人はある程度見返りを想定して Give している。
でも Give してもらったことで相手方から Branded されて、それによって想定しない Give が返ってくることがある。そういう見返りを想定しない贈与によって発生する予測不可能性がコンテンツマーケティングの醍醐味だと思うので、「何がどうアトリビュートしているか」を判断の拠りどころとするのは改めて難しいことなんだな〜と思います。何を言っても後付けでしかないというか。
今の話で、個人的なエピソードを思い出したので話してもいいですか?

もちろんです。ぜひぜひ。
東京のどこかで天ぷら店をやっているおじさんの YouTube チャンネルがあって、結構その方のキャラクターが好きでよく見ちゃうんです。でも、自分の生活圏内ではない場所のお店なので、食べには行かないんですよ。今までも行ったことないし、今後もおそらく行くことはない。
でも、その方にとっての主たるビジネスはやっぱり飲食店の経営です。動画はめちゃめちゃ見ていて好きなのに、私は何にも関われない。うーん、と。

残念ですけど、そういうことってありますよね。
なんですけど、ある時その方が書籍を出したんですよ、まかないレシピ本。

おお!
だからすぐ Amazon で買いました。これもある種、おもしろい動画として Give してくれたことで生まれた関係性だと言えるのかなと。

まさにそうですね。その本を伊東さんが買ってるってことを、その方は知らないわけじゃないですか。
もちろんご存じないはずです。

でもそこに伊東さんの感情が動き、アクションに結びついたわけなので、アトリビューションは見えにくいけど、確実にあった。
そういうことになりますね。
その時はクリエイター側の人たちのビジネスモデルというか、チャネルミックスをどう作って稼ぐかみたいなことを考えていたのですが、お話を聞いて Give & Given という見方もあるよな〜と思いました。

チャネルが拡がることでカテゴリーが越境しますよね。飲食店のお客さんではないんだけど、その外側にいた伊東さんに、レシピ本を出すことで届いたという。
JADE のニュースレターも、SEO 周りの近いコミュニティだけでなく、広告がご専門の岡田さんに、東京だけじゃなくて金沢まで届いたというのが、まさに越境ですね。
自分のいるコミュニティ外に出ていくのってすごく難しいんですよね。外が嫌なんじゃなくて、そういう機会が得にくかったり、手段がうまくつくれていないとかで、結果的に安住しちゃうことが多いので。でも自社の活動でそういう外側に向かうきっかけを持てたとしたらすごくうれしいですね。

広がっていると思います。少なくとも私はニュースレターで JADE さんの印象が変わりましたし。「怖(強)そうだな」から「楽しそうだな」って(笑)。
「楽しい」はありますね。毎回書くのは苦しいんですけど、行為そのものは楽しいです。

そうか。さっきは「偉い人が覚悟をもって行うのがコンテンツマーケティングだ」っていう話がありましたが、「覚悟」よりは「楽しい」のほうがいいですね。楽しいほうがサスティナブルな気がする。
そうですね。コンテンツマーケティングは楽しいもの。そういう姿勢でやっていきたいですね。楽しいほうが続きますから!
対談を終えて
伊東さんとは実は初めて長くお話しましたが、以前から定期的に話していたような、そんな心地よい雰囲気を感じました。
コンテンツマーケティングはあまり詳しくない領域ですが、話しながら「自分が今までやってきたことは、コンテンツマーケティングの文脈にも一部当てはまるかもしれない」と思うことがありました。記事を通じて知ってくださる方が増えたり、そこから拡がる関係性もこれまでたくさんありました。
それらは定量的な ROI を目指して始めたことではありません。「楽しい」「やりたい」「伝えたい」、そういう衝動を企業の営みに加えていった結果、たまたまそれに反応する人が返して(Given)くれている。お互いに Give を感じている状態が健全なのかもしれません。
伊東さんや JADE さんとはこれからも似たような話をする機会があると思うので、そのときはまた続編として記事にまとめたいと思います。 伊東さん、今後ともよろしくお願いします!