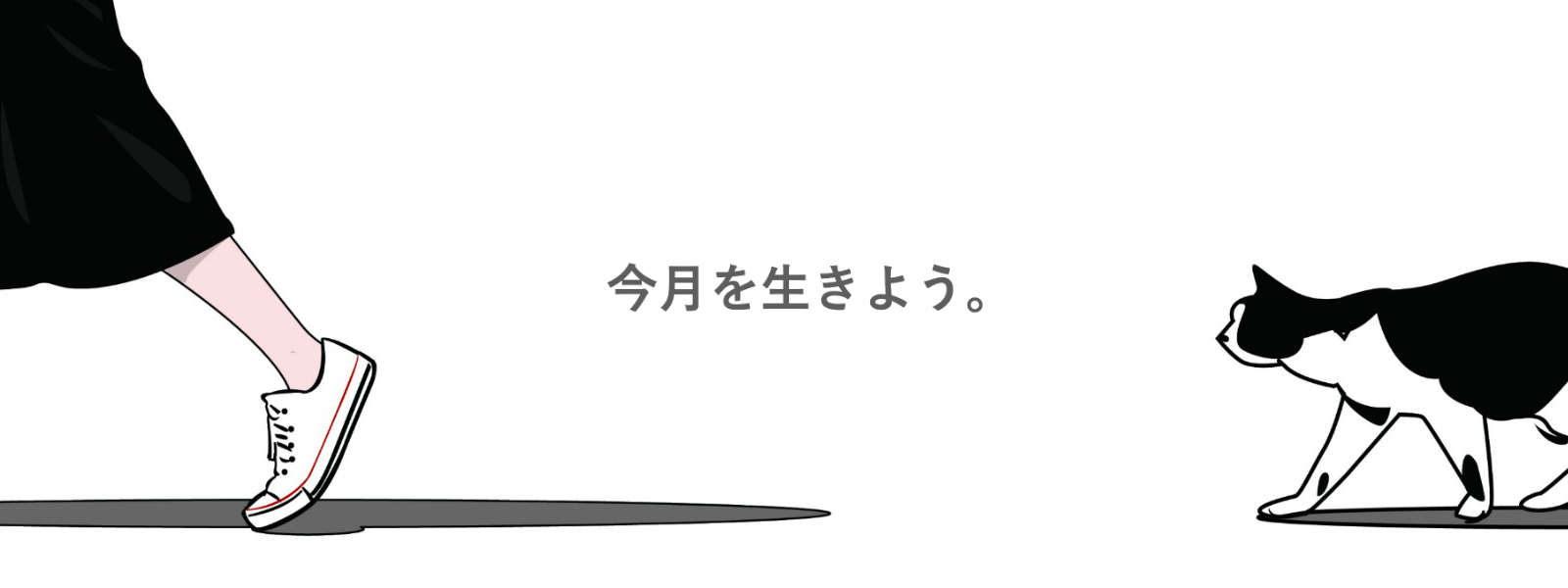「広告の有効性」という項目が Google広告にある。広告をつくっていると目にすることが多いですよね。

その名前からしてなんだか重要そうだし、「有効」の対義語は「無効」だから、つまり低いと効果なしということで広告が出なかったりするのかな…?などと不安な気持ちになってしまう人もいるらしい。
先に言っておくと、ここでは「気にしなくていい」と断言してしまおう。少なくとも私は気にしていない。もちろん気にしたほうがいい場面もあるにはあるだろうが、気にしなくていい場面のほうがそれ以上に多いと感じるからだ。
さまざまな意見はあるのは承知のうえで、なぜ気にしなくていいのかを書いていこうと思う。
気にしなくてもいい理由
気にしなくてもいい理由の大半は実は「1.実績に関係がない」なのだが、せっかく記事を書くのでもう少し掘り下げていくと、以下の 3つに大別できると思う。
1. 実績に関係がない
- パフォーマンスとの関連性が低い
- 広告ランクに直接影響しない
2.キャンペーン設計や運用とのミスマッチ
- 恣意的に部分一致へ誘導しやすい
- 一部のキャンペーンにはそぐわない
- 「関連性」をミスリードする
3.見えない負債が増える可能性がある
- パターンマッチングを強化するだけになる
- 矛盾するルールによる落とし穴がある
以降でそれぞれの理由について考えていきたい。
1.実績に関係がない
まずは実績との関連性が低いことが挙げられる。気にしなくていい理由の大半はこれに尽きる。
会議には顔を出すけど一切発言しない重役のように、重要そうな顔をしながら実はパフォーマンスとは何も関係がないのだ。尊重はするけど意思決定に加える理由がない。
ただ、そうとは思えないような記述がヘルプにあるので勘違いしやすいのだと思う。「レスポンシブ検索広告に関する広告の有効性について」と題したヘルプページには、以下のような言葉が並んでいる。
広告の有効性が高いほど、広告のパフォーマンスを最大化できます。
レスポンシブ検索広告の有効性を「要改善」から「優良」に改善した広告主様は、コンバージョン数で平均 12% の増加を達成しています*。
https://support.google.com/google-ads/answer/9921843?sjid=17564362663334362106-AP
「有効性」いう語彙からにじみ出る無言の圧力や、上記のようなパフォーマンスに関連することを匂わせる表現によって、「広告の有効性」は重要な指標で無視してはいけないのでは…?と感じてしまう。
ただ、よーく読むと以下のような表現も見つけることができる。(太字は筆者による)
広告の有効性の評価は、広告の配信の要件には直接は影響しません。むしろ、広告の作成または編集の際に広告の有効性の評価を活用して、広告を改善し、パフォーマンスを最適化できます。
https://support.google.com/google-ads/answer/9921843?sjid=17564362663334362106-AP
どっちやねんと言いたくもなるが、とにかく引用にあるとおり、「広告の有効性」は配信の要件には直接は影響しないと明言されている。
つまり、有効性が低くても配信が制限されたり、配信要件を満たさないということはない。
広告代理店などでたくさんのアカウントを見ている人なら同意してくれると思うが、広告の有効性が低くても、クリック率が高かったりコンバージョンをバシバシ稼いでくれる広告は実際に存在する。要はそういうことなのだ。
ちなみに、引用にある「広告の配信の要件」とは何だろうか。これは(審査等を除けば)ご存知のとおり広告ランクのことを指している。
広告ランクは大雑把に「入札単価 × 品質」だと憶えておけばいいが、ヘルプの記載に沿うと以下の6つの要素が考慮される。長いがそのままが引用する。
広告ランクのスコアは、大まかに次の 6 つの要素に基づいて決定されます。
https://support.google.com/google-ads/answer/1722122?hl=ja
- 入札単価 – 入札単価とは、広告のクリック 1 回に対して最大でいくらまで支払ってもいいか、広告主様が指定したものです。通常、最終的な支払い金額はこれより少なくなります。入札単価はいつでも変更できます。
- 広告とランディング ページの品質 – 広告とそのリンク先のウェブサイトがユーザーにとってどれほど有用で関連性が高いものであるかも判断基準となります。広告の品質評価の結果は、品質スコアでわかります。品質スコアは Google 広告アカウントで確認できます。
- 広告ランクの下限値 – 常に質の高い広告を掲載するため、表示される広告が満たすべき最低限の基準を定めています。
- オークションにおける競争力 – 同じ順位で競合する 2 つの広告の広告ランクが同じ場合、それぞれが同じ順位を獲得する確率はほぼ同じになります。2 つの広告主の広告間の広告ランクの差が大きくなると、ランクの高い広告は勝つ確率は高くなりますが、その位置を獲得する確率を高くするために高いクリック単価を支払うこともあります。
- ユーザーが検索に至った背景(コンテキスト)– 広告オークションにおいてコンテキストは重要な要素です。広告ランクを算出する際は、ユーザーが入力した検索キーワード、検索時のユーザーの所在地、使用しているデバイス(例: モバイル デバイスやパソコン)、検索した時刻、検索語句の性質、同じページに表示される他の広告と検索結果をはじめ、さまざまなユーザー シグナルと属性が考慮されます。
- 広告アセットやその他の広告フォーマットの効果 – 広告を作成する際は、サイト内の特定のページへのリンクや電話番号など、特定の情報を広告に追加できます。この機能を「広告アセット」と呼びます。Google 広告では、広告主様が追加したアセットやその他の広告フォーマットの見込み効果も考慮されます。
しつこく繰り返して申し訳ないが、「広告の有効性」はこれらの要素には影響しないということだ。
有効性が高くなったからといってオークションにおける競争力が上がるわけではないし、低いから競争力が下がるわけでもない。もちろん広告の品質にも直接の影響はないし、有効性が高いから入札単価が安く済むわけでもない。
Google のスポークスパーソンである Ginny Marvin 史も、Twitter(現:X)で以下のようなポストをしている。
Hi Nate, A few things to clarify here:
— AdsLiaison (@adsliaison) April 12, 2024
– This is not a new warning.
– Ad Strength is not used in Ad Rank and is *not* a “factor in stopping a keyword from going to auction due to Ad Rank”.
– Ad Strength is a distinct diagnostic tool. And to reiterate, it’s not a factor in the…
上掲のスレッドは広告表示に関する質問への返信の一部分なのだが、ここでの回答が「広告の有効性」が実績に関係ないことの証拠になっている。(日本語は筆者による雑訳)
– Ad Strength is not used in Ad Rank and is *not* a “factor in stopping a keyword from going to auction due to Ad Rank”.
– Ad Strength is a distinct diagnostic tool. And to reiterate, it’s not a factor in the auction. It simply helps indicate the diversity and relevancy of the assets available to maximize the number of ad combinations that may show for a query. More combinations available typically means you’ll have more opportunities to serve relevant ads in more auctions.
– 広告の有効性は広告ランクでは使用されず、「広告ランクによってキーワードのオークション参加が止められる要因」でも【ありません】
– 広告の有効性はあくまで診断ツールです。繰り返しになりますが、オークションの要素ではありません。検索クエリに対して表示される可能性のある広告の組み合わせを最大化するために、アセットの多様性と関連性を知るのに役立ちます。一般的に、利用可能な組み合わせが多ければ多いほど、より多くのオークションで関連性の高い広告を配信する機会が増えます。
https://twitter.com/adsliaison/status/1778861620267037112
Marvin 氏も「広告の有効性」はあくまで多様性と関連性の診断であり、結果を保証するものではないと明言している。ヘルプの解釈で合っているということだ。
たとえば、B2Bの広告でよく行う【法人向け】といった記述も、【】で法人を強調することによって個人ユーザーがクリックしないよう意図的なフィルタリングとして記載しているわけだが、もし「広告の有効性」がオークションに作用してしまうと、商売に結びつきにくい個人のインテントであっても「【法人向け】と書かない見出しも入れないと多様性が低いのでオークションに参加できない」ことになってしまう。そんな仕組みの配信システムでは費用対効果がいつまで経っても合わないので、そのうち広告主はいなくなってしまうだろう。
というわけで、「広告の有効性」はパフォーマンスとは直接の関係がないのだから、低くても実績が見合ってるなら自信を持って継続すればいいと思う。アラートに惑わされる必要はない。
個人的には、ヘルプの表現はもう少しわかりやすくしてほしいし、できるなら「広告の有効性」という対訳も変えてほしいと思っている。元の名前は「Ad Strength」なわけだから、直訳すれば「広告の強度」だし。強度じゃ意味わからんということなのだと思いますけど。。。
2.キャンペーン設計や運用とのミスマッチ
パフォーマンスに関係ないのであれば無視すればいいはずなのだが、とにかくヤツは管理画面の至るところに現れる。しかも元々がアラートの役割なのでほんのりと煽り成分があるのだ。
油断するとキャンペーンのおすすめ項目にしれっと入ってくる抜け目のなさもあるので、気づくと毎日見ているということになりかねない。低くても大丈夫だと知っていても、ずっとテストの答案を晒されているような体験はあまり気持ちのいいものではない。

なぜ「広告の有効性」がこれだけプッシュされているかというと、前述のとおり広告の多様性に寄与するからだ。
「たくさんアセットを詰め込むのが正義」という価値観を押し出せば押し出すほど、広告がオークションに参加する機会を増やすことにつながる。実際に、検索クエリとマッチする広告アセットが多ければ多いほど、機械的に計算される関連性は高まり、カバレッジは増えやすい。
「広告の有効性」は、広告自体が動的になったことで生まれた指標だ。検索広告が固定長の拡張テキスト広告から可変長のレスポンシブ検索広告へと移ってから、1つの広告で表示できる見出しや説明文のパターンは劇的に増えた。
仮に、レスポンシブ検索広告のアセットの上限である「見出し15本、説明文4本」をすべて入れた広告を作成した場合の、広告のパターン数を挙げてみると以下のようになる。
見出しが2件、説明文が1件→ 15P2 × 4P1 = 840通り
見出しが2件、説明文が2件→ 15P2 × 4P2 = 2,520通り
見出しが3件、説明文が1件→ 15P3 × 4P1 = 10,920通り
見出しが3件、説明文が2件→ 15P3 × 4P2 = 32,760通り
————————————————————
上記の合計→ 840 + 2,520 + 10,920 + 32,760 = 47,040通り
なんだかすごい組み合わせ数になってしまった。
加えて、現実の運用ではサイトリンクや画像などのアセット(旧:広告表示オプション)の組み合わせもあり、最近は見出し1本表示なんかも試しているので、理論値としてのパターン数はかなりの数になるのは間違いない。(中学か高校の数学で場合の数的なものをやった気がするのですが… 計算間違ってたらすみません)
もちろん現実的には見出しが 3本出ることは少ないし(そもそも視認できないことが多い)、見出しを 15本入れている広告は少ないだろうから、こんなに大量のパターンになることはまずない。見出しをピン留めすれば重複度のぶんだけパターン数も大幅に少なくなる。
実際はオークション実績を元に収斂されていくので「よく出るのは◯通り」程度にまとまることが多いが、可能性だけでみればこれだけの数になるのだ。拡張テキスト広告とは比較にならない多様性があるのがレスポンシブ検索広告なのである。
部分一致への誘い
これほどに多様性があるレスポンシブ広告は、当たり前だが自動入札や部分一致と相性がいい。
自動入札と部分一致の蜜月については 不況下でも自社のCPCが高いままなのは、ひょっとして自動入札のせいかもしれない という記事に書いたので詳細は省くが、どれだけキーワードの解釈と予測の精度が高まっても、表示する広告がいつも同じでは関連性は高まらない。
広告のパターンを増やすには広告主側が入力する情報が増えないといけないが、広告そのものが静的(検索でいえば以前のテキスト広告)だと、入力の数とパターン数がイコールになるため、広告の本数分しかバリエーションが増えない。だから、いくらクエリのカバレッジを上げても関連性は高まりにくかった。

そこで考えたのが、広告自体を動的にするということだった。レスポンシブ広告の登場によって、複数のアセットを入力してひとかたまりとすることで、その中でアセットごとのパターンをクエリに合わせて自動的に組み合わせることで広告を合理的に動的に変えていくことに成功した。
ただ、似たようなアセットばかり入っていてもパターンだけ増えて関連性は上がらないから、明示的に違う言葉や表現を使うインセンティブを設計する必要がある。クエリと結びつく広告の幅が広がるように仕向けることで、マッチングの精度は上がりやすくなる。
これが「広告の有効性」が生まれた背景である。

これは言いかえれば部分一致や自動入札と共犯関係にある仕組みだ。多様性を後押しすることでクエリのカバレッジが上がり、予算をより使って、オークションを活性化することにつながる。Google が広告主にしてほしいことを促す仕組みだといえる。
一部のキャンペーンにはそぐわない
「広告の有効性」に従うことは、部分一致で大量に回す広告グループや予算が潤沢にあるキャンペーンでは有効に作用すると思う。ただ世の中はそういう広告ばかりではない。
指名検索のようなユーザーの目的や意図がはっきりしていて、広告主もオーソリティを明示でき、トップページや製品ページなどわかりやすい場所に誘導する明確な理由がある場合には、自動化や多様な広告表現はマイナスに作用する可能性がある。
ゴールが決まっているなら、いろんな表現でユーザーを惑わせたり不安にさせる必要はないのだ。堂々と【公式】と書けばいいし、キャッチコピーがあるなら常にそれを使うべきだ。そのほうがユーザーファーストだし、認知にも貢献する。結果的にクリック率も安定するだろう。
Google がいう関連性は、あくまで機械的なキーワードとアセットのマッチングのことを指している。でも実際に検索するのは人間で、広告を見るのも人間なので、もし検索クエリから求める情報が明確に類推できるのであれば、広告のパターンは無理に増やす必要はない。迷わずそこへ誘導する言葉を使うべきだろう。関連性をミスリードしてはいけない。
3.見えない負債が増える可能性がある
「広告の有効性」はアセットの多様性を示すと書いた。有効性を追いかけることは、つまりパターンの無限に広げて機械学習で類推していく作業への暗黙の同意を意味する。
パターンマッチングが強化されることで、確かに理論上は数字が向上しやすい。一方で、これによって「こういう状況のユーザーに、この言葉を届けて、この商品やサービスを知ってもらおう」といった一連のマーケティング的な準備や努力は相対的に軽視されやすくなる。動的で複雑なものを受け入れると、ターゲットは定めるのではなく現れるものに変わる。それは「考えなくていい」というメッセージと混同しやすい。
ヘルプにもあるとおり、「広告の有効性」はあくまで一般的な成功パターンに基づいたスコアリングでしかないため、高いスコアのアセットはどうしても似たような表現に落ち着いてしまう。多様性を突き詰めようとしたら量産型のモブばっかりになってしまう危険性があるのだ。端的にいえば「キーワードをアセットに含めよ」と言っているに過ぎない機能なのだから。
これは広告の役割の一つである「新たな発見や価値を提示する」「気づいて心に留めてもらう」といったアプローチを阻害する要因になりかねない。と書くと老害すぎるだろうか。。。
考えなくてもシステムがマッチングしてくれるという前提では、検索しているユーザーのマイクロモーメントを想像するインセンティブが働かない気がする。最適化によって見えない負債が増えないといいなとは思う。
矛盾するルール設計
レスポンシブ検索広告では見出しや説明文を固定する「ピン留め」を行うと「広告の有効性」は下がる。(パターンの最大数が減っちゃうので)
ところが、2024年から正式に発表された「見出し1本だけで表示されることがあるよ」という仕様によって、「広告の有効性」にある種の落とし穴が生まれることとなった。
多くの広告主は、「広告の有効性」と広告文としての意味を両立させるために「見出し2本がセットになって日本語として意味が通る」ように広告を作成している。
それが、上記の「見出し 1本のみの表示」が解禁されるようになって、図らずも意味不明な広告が配信されるという事例が散見されるようになった。2本揃ってはじめて広告文として成立するのに、片方の 1本だけで出てしまうのだ。もはやホラー小説か落語のような展開である。おそろしい。
「広告の有効性」を上げようとしてたくさんアセットを詰め込んだ結果、謎の広告文が配信されてしまいクリック率やコンバージョン率が下がるのは本末転倒だ。こういう制度上の矛盾がある以上、ピン留めすると下がるような「広告の有効性」を気にしろというのは無理がある。(同時に、プラットフォームには混乱をなるべく回避する責任があると思います)
「広告の有効性」は気にしなくていい
というわけで、「広告の有効性」は気にしなくていいということをつらつらと書いてきた。思いのほか長くなってしまった。
もちろん、これが無駄な機能というわけではない。たとえば、広告作成の経験が浅ければ、広告の有効性のガイドラインに従うことで、そうでない場合よりも成果が上がる確率が高まることが期待できる。
ただ、それでも「広告の有効性」はパフォーマンスに直接の影響はないわけだし、一般的なベストプラクティスが自社アカウントの成功を保証するわけでもない。「有効性」という強い言葉に惑わされやすいが、品質スコアを KPI にしてはいけないように、「広告の有効性」もまた評価の対象にしてはいけない。
広告は管理画面上のインジケーターを上げるために行うわけではないのだから、貴重な広告予算はあくまで数字の先にある人間の行動のために使われるべきだと思う。変な指標に惑わされず、よい広告が人々の生活を豊かにする未来を信じたいですね。